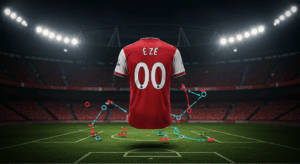はじめに
(出典:eintracht frankfurt、堂安律公式instagram)
日本代表の堂安律が、アイントラハト・フランクフルトへの移籍を決断した。5年契約、移籍金2100万ユーロという条件は、日本人選手の歴代移籍金として4位の記録となり、フランクフルト史上でも5位の高額移籍となった。この数字が示すのは、単なる補強ではなく、チームの核として期待される堂安への信頼である。
今回は、この移籍を戦術的観点とキャリア戦略の両面から分析し、なぜこのタイミングでのフランクフルト移籍が堂安にとって最適解だったのかを探る。
移籍決断の戦略的背景
W杯への逆算思考
堂安の移籍決断の根底にあるのは、2026年W杯への明確なビジョンだ。「W杯が一番の夢」と公言する堂安にとって、この移籍はキャリアのゴールから逆算した戦略的選択といえる。
出場機会の確保という絶対条件
W杯でのパフォーマンスを100%に持っていくためには、継続的な試合出場が不可欠だ。しかし、ここで重要なのは単なる出場時間ではなく、「環境変化によるロス時間の最小化」という視点である。
堂安は移籍理由について「戦うリーグを変えると環境が変わってしまうため、慣れに時間がかかってしまう」と述べている。これは非常に戦術的な判断だ。ドイツ・ブンデスリーガ内でのステップアップにより、リーグの特性やレフェリングの傾向、戦術的トレンドへの適応時間を最小限に抑えることができる。
フランクフルトのビジョンとの一致
移籍先としてフランクフルトを選んだ決定的な理由は、ニコラス・トップメラー監督の明確なビジョンにあった。「監督のビジョンがはっきりとしているフランクフルトならすぐに慣れると思った」という堂安の言葉は、戦術的な適合性を重視した判断を示している。
さらに、クラブから「チームのラストピースが律である」と伝えられたことは、単なる戦力補強ではなく、チーム完成への最重要ピースとしての期待を意味する。CL出場権も手にしたフランクフルトで、堂安は欧州最高峰の舞台でのプレー機会も得ることになった。
(出典:堂安律公式YouTube)
堂安律の歩み ~オランダからドイツへの戦略的キャリア~
堂安のキャリアパスは、計画的なステップアップの典型例だ。
ガンバ大阪時代(〜2017年) 10代という若さで海外挑戦を決断
オランダ時代(2017年〜2021年)
- フローニンゲン(レンタル→完全移籍2017~2019)
- PSV(2019年〜2021年)
ドイツ時代(2021年〜)
- アルミニア・ビーレフェルト(レンタル、2020-21シーズン)
- フライブルク(2022年〜2025年)
- アイントラハト・フランクフルト(2025年〜)
オランダでの技術的基盤構築から、ドイツでのフィジカルサッカーへの適応という流れは、現代的なキャリアプランニングの好例といえる。
24-25シーズンの飛躍 ~数字が語る成長~
(出典:ElevenManagement、堂安律公式instagram)
フライブルクでの最終シーズンとなった24-25は、堂安にとって転機となった。
リーグ戦成績
- 出場試合数:34試合
- ゴール:10
- アシスト:8
特筆すべきは海外挑戦初の2桁ゴール達成だ。年々GA数を増やしてきた堂安が一つの指標である10Gを達成したことは非常に重要なことだ
チーム成績でもフライブルクをリーグ5位に導き、堂安の貢献度の高さを数字で証明した。
フランクフルトの戦術的変革と堂安の役割
24-25シーズンのフランクフルト
基本フォーメーション:4-4-2
フランクフルトの戦術的特徴は、縦に速いショートカウンターにある。2トップにマルムシュ(冬にマンチェスター・シティへ移籍)とエキティケ(夏にリヴァプールへ移籍)といった若い選手を配置し、スピードを活かした攻撃を展開していた。
この戦術により、チーム初のCL出場権を獲得(リーグ3位)。しかし、主力2人の移籍により戦術的再構築が必要となった。
25-26シーズンでの堂安の戦術的位置づけ
トップメラー監督の戦術哲学
ニコラス・トップメラー監督の特徴的な戦術思想が、堂安の起用法を決定づける。
- 利き足逆サイドでのウィング起用を好んでいるため左利きの堂安は今まで通り右サイドで起用されると考える
- サイドバックとの連携重視 オーバーラップやアンダーラップを活用した攻撃パターン
- 前線からのプレッシング 守備をさぼらない献身的な動きが評価された要因
堂安の持つ「常に献身的な動きをする」特徴は、トップメラーの求める前線プレッシングシステムに完璧にフィットする。運動量豊富な堂安は、フランクフルトの戦術にとって不可欠なピースなのだ。
ポジション争いの分析 ~クナウフとの競争~
(出典:Ansgar Knauff公式instagram)
アンスガー・クナウフ との比較
右ウィングでの堂安のライバルは、アンスガー・クナウフだ。
クナウフの特徴
- 武器:爆発的なスピード
- 守備:前監督グラスナー時代に右WBでも起用される献身性
- 24-25成績:リーグ戦30試合4G6A
比較分析
| 項目 | 堂安律 | クナウフ |
|---|---|---|
| ゴール数 | 10G | 4G |
| アシスト数 | 8A | 6A |
| 決定力 | 〇 | △ |
| スピード | 〇 | ◎ |
| 戦術理解 | ◎ | 〇 |
クナウフの4ゴールに対し、堂安の10ゴールは圧倒的な差を示している。2100万ユーロという移籍金を考慮すれば、堂安のスタメン起用は既定路線といえる。
フランクフルトの経営戦略と堂安の未来
(出典:堂安律公式instagram)
ブライトン型経営モデル
フランクフルトは近年、ブライトンのような戦略的な選手育成・売却モデルを採用している。
実例
- コロムアニ
- パチョ
- マルムシュ
- エキティケ
この戦略では、契約が残っていても選手が高値で売れるなら躊躇なく売却する。堂安にとって、これは更なるステップアップへの道筋を意味する。
長谷部誠の背番号20 ~象徴的意味~
(出典:EintrachFrankfurt、堂安律公式instagram)
堂安が着用する背番号20は、フランクフルトのレジェンドであり元日本代表キャプテン長谷部誠の番号だ。
長谷部が築いた「ブンデスリーガでの日本人選手の地位」を継承し、さらに発展させる役割を期待されている。戦術的な貢献だけでなく、精神的支柱としての役割も込められた番号といえる。
まとめ ~戦略的移籍の完璧な執行~
(出典:EintrachFrankfurt公式instagram)
堂安律のフランクフルト移籍は、単なるステップアップではない。W杯という明確な目標から逆算した戦略的キャリアプランニングの結果だ。
成功要因の分析
- 環境変化の最小化:ドイツ国内でのステップアップ
- 戦術的適合性:トップメラー監督のビジョンとの一致
- 明確なポジション:チームのラストピースとしての位置づけ
- 数字による裏付け:2桁ゴールによる実力証明
- 将来性:フランクフルトの経営戦略との合致
この移籍により、堂安は2026年W杯に向けて最適な環境を手に入れた。CL の舞台での活躍、そして代表での中心的役割を経て、さらなるステップアップへの道筋も見えている。
日本サッカー界にとって、堂安の成功は新たなキャリアモデルの確立を意味する。データと戦術に基づいた計画的なキャリア構築こそが、現代フットボーラーに求められる要素なのだ。
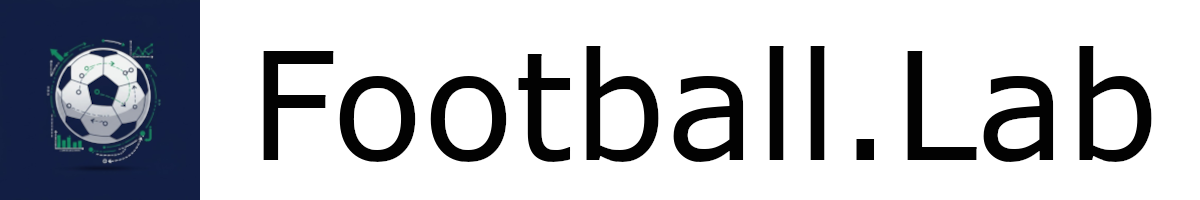
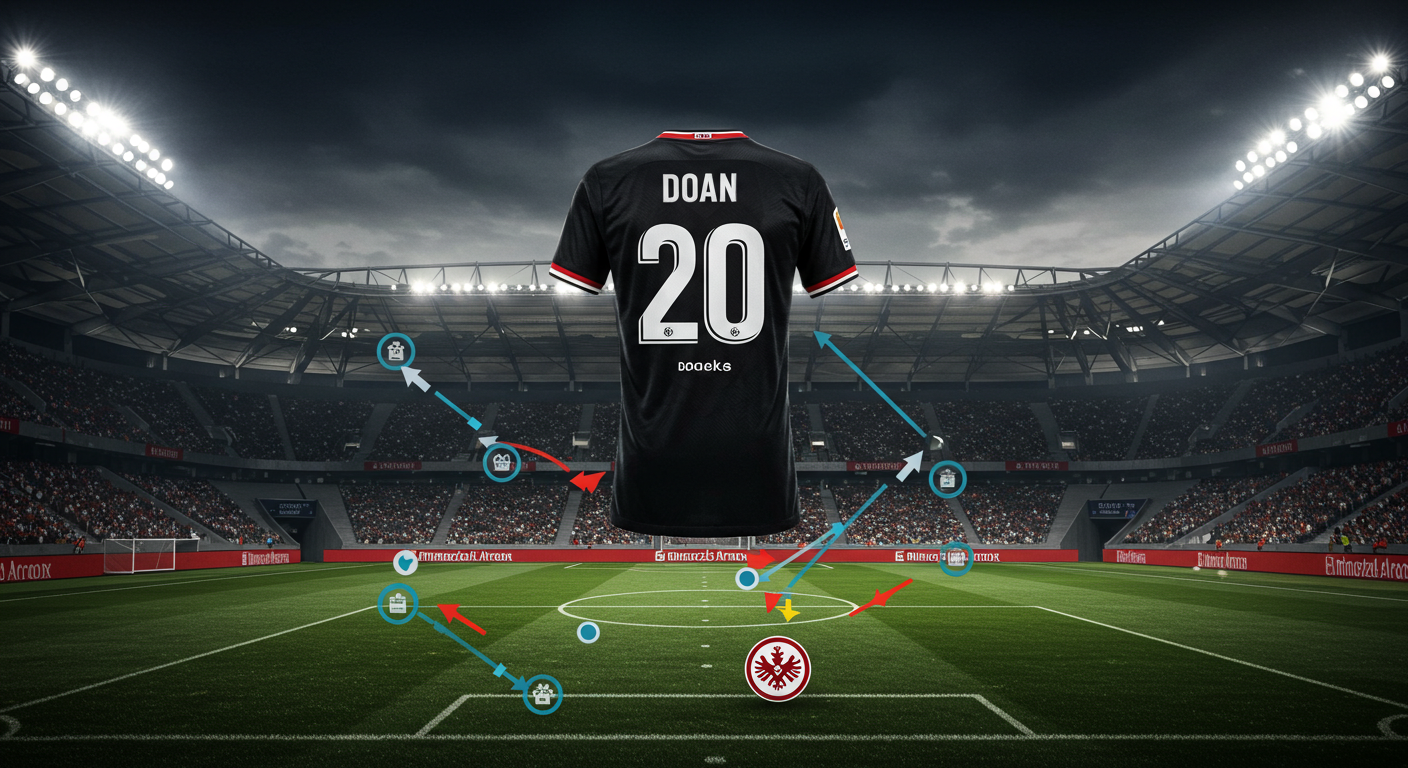
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b60740c.4516094f.4b60740d.eac5ffc5/?me_id=1235962&item_id=10218272&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkurashikenkou%2Fcabinet%2F10833992%2Fimgrc0093953372.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b60960a.c2ff2571.4b60960b.b0032d58/?me_id=1413042&item_id=10000187&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhitidear%2Fcabinet%2F10065696%2F10914652%2Fbreezez-2094.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)